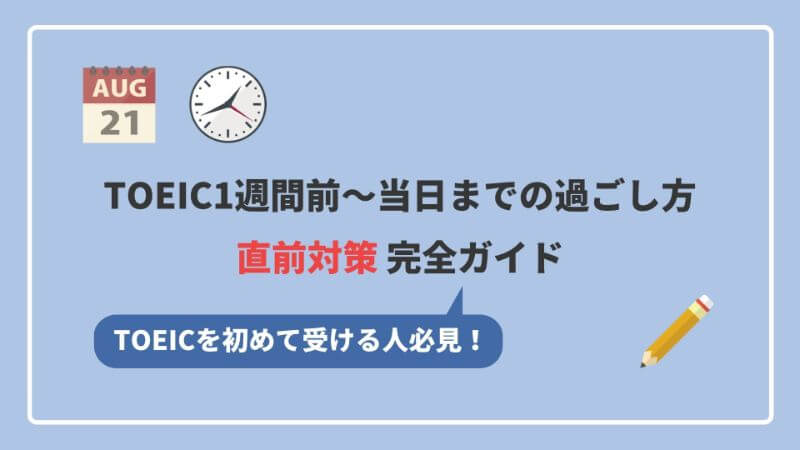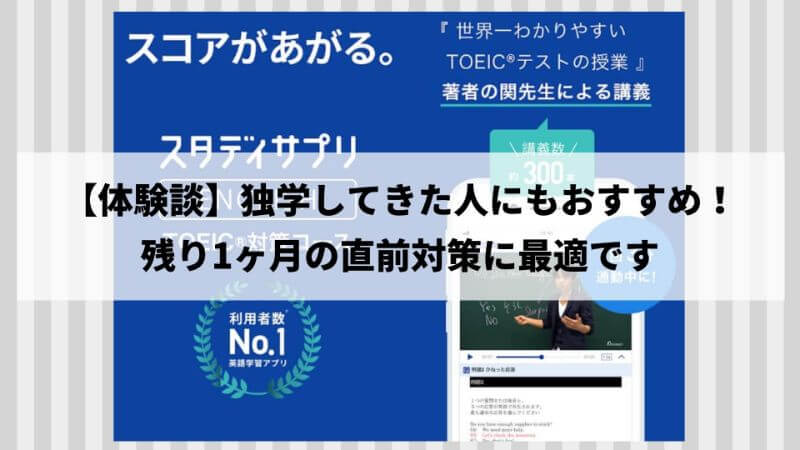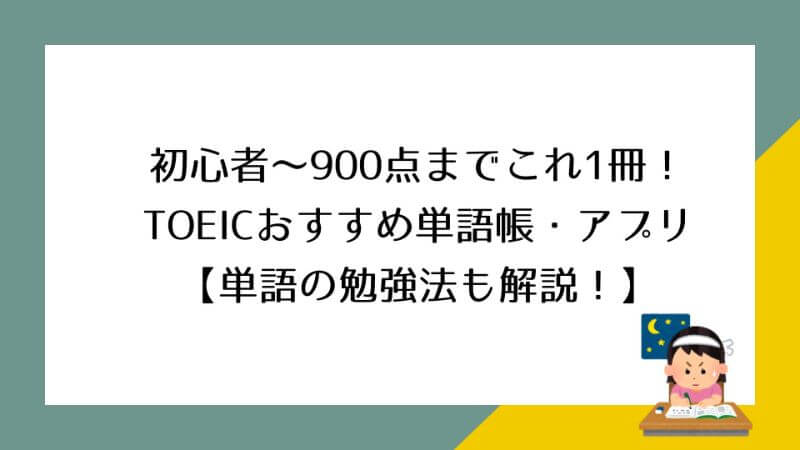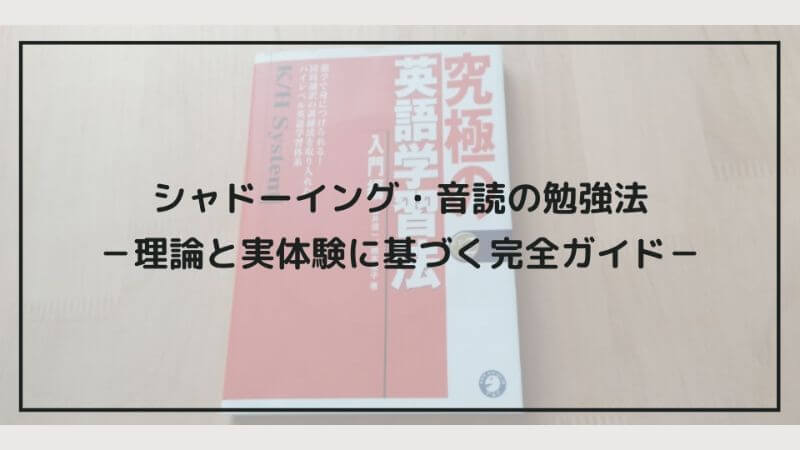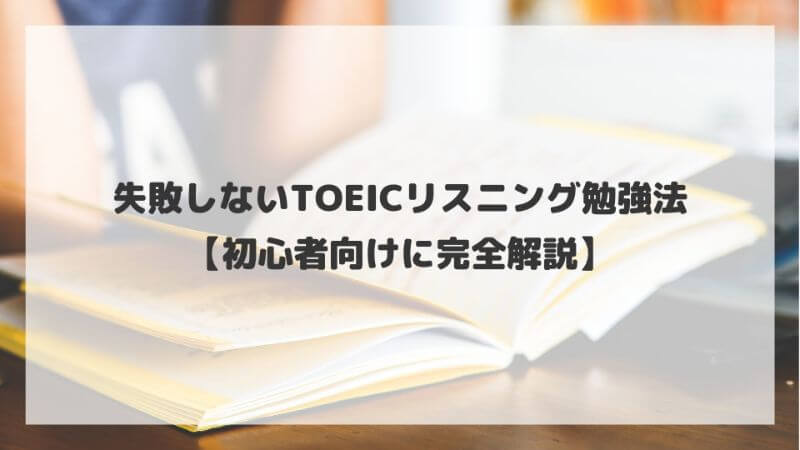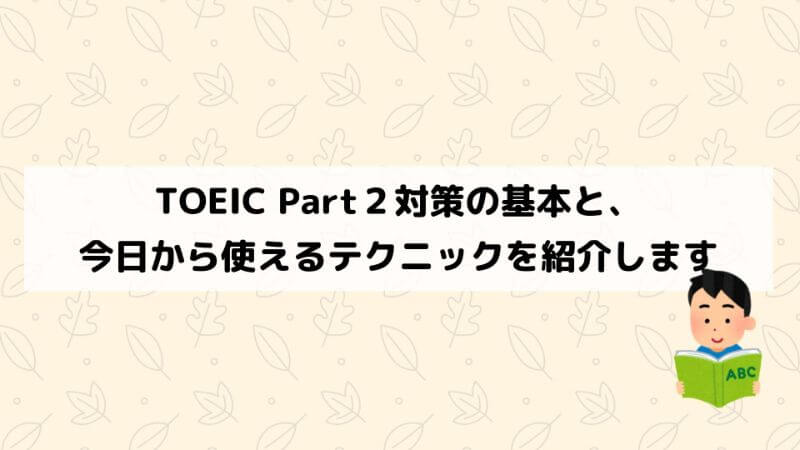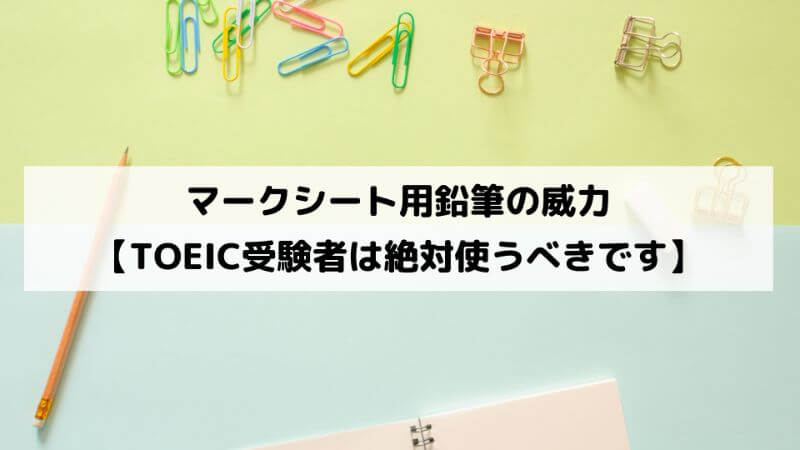来週はいよいよTOEICの本番!皆試験直前ってどんな勉強や準備をしてるんだろう?
TOEIC直前期にやるべきことは、以下の2つに尽きます。
- タイムマネジメントの再確認
- 今まで勉強した内容の総復習
タイムマネジメントについては、公式問題集を時間を測って解くのがベストです。
総復習については、まともにやっていたら時間がかかるし、参考書の数が多ければ多いほど大変ですよね。
そんな人には、30分で自分の苦手箇所だけを総復習できる「ファイナルペーパー」の作成をおすすめします。
ここでは、
- 試験1週間前から前日・当日までの過ごし方
- ファイナルペーパーの作り方、活用法
- 簡単!やるだけで10点上がる!試験テクニック
について、解説していきます!
私は以前海外に住んでいて、帰国後はメーカーの海外部門で働いています。
TOEICは現在880点で勉強中の身ですが、これまで10回以上TOEICを受けています。※その後英検1級を取得しました。

この記事で、TOEIC直前期にやるべきことは全て書いています。最後の悪あがきを考えている方も、ぜひ最後まで読んでみてください!
もくじ
TOEIC1週間~2日前 | 直前期の準備と総仕上げ

TOEIC1週間前になったら、今まで勉強していたことの総復習をしましょう!
復習する内容は、
- 暗記があやふやで、前日にもう1回見返しておきたいこと
- 時間配分の感覚
特に時間配分は、頭で分かっているだけでは対応できないため、1週間前に改めて制限時間の感覚を復習する必要があります。

以下で、それぞれ深堀して解説していきますね!
ファイナルペーパー作り | 時短で総復習する必須アイテム
ファイナルペーパーとは、試験直前にサッと目を通しておきたい情報をまとめたペーパーのことです。
- ペーパーを作る過程で、今までの学習の総復習ができる ⇒ 一石二鳥!
- 試験当日、会場に参考書を何冊も持ち込む必要がない ⇒ 当日の荷物が軽くなる!
- 試験開始直前に復習すべきことが一目瞭然で分かる ⇒ 30分で総復習できる!
TOEICの勉強をしていて、1冊の参考書の中でも、特に復習したいページは限られていると思います。

それを寄せ集めたものがファイナルペーパー、いわばカンペです!笑
ファイナルペーパーは、持っている参考書や問題集を全部チェックしながら作るので、1週間前から取り掛かりましょう!
思っている以上に時間がかかります。
以下は前回のTOEICの直前に、私が実際に作ったファイナルペーパーです。

内容は試験開始直前に見ておきたい情報なら、基本的に何でもOKです。

最初のころは「have (人) 動詞の原形」とか、文法的なことを書いたりしてました。
今では単語や熟語を中心に、暗記し切れていないものをリスト化しています。

↑のようにパソコンで作れば、内容を足したり消したりして、次回のTOEICでも使い回せるのでおすすめです。

ファイナルペーパーは時短で総復習できるので、ぜひ作ってみてください!
公式問題集で模試をやる | 時間配分の再確認
各設問に何分かけるのか、タイムマネジメントの復習もしておきましょう!
やり方はシンプルで、
- 公式問題集などの本番形式の模試を使う
- きちんと時間を測り、時間配分を確かめながら解く
- 採点と復習、時間配分の反省点など振り返り
時間配分を確かめるのが目的なので、リーディングセクションだけでもOKです。

私は1週間前の週末に、まとまった時間を取ってやることが多いですね。
TOEIC前日 | 苦手箇所の総復習【最後の悪あがき】

前日にやるべき一番大切なことは、ファイナルペーパーを使った総復習です。
その他のリスニングやリーディングは、時間があれば、明日の本番に向けた準備運動程度にやればOKです。

前日は最後の悪あがきと思って、もう一息頑張っていきましょう!
以下で詳しく個別に解説していきます!
単語・熟語 | ファイナルペーパーで30分総復習
ファイナルペーパーを使って、これまで勉強してきた全範囲を総復習します。
復習の仕方としては以下の流れです。
- ざっと1周し、あやふやな箇所にチェックを入れる
- チェックを入れた箇所をもう1周

ポイントはここで覚えようとせず、明日の当日やるべきことをファイナルペーパーの中から絞り込むことです。
A4で5枚以上になる人もいると思いますが、深くやり出すと切りがないので、ざっと30分くらいで終わらせましょう!
リスニング | 公式問題集を使って苦手箇所のシャドーイング
時間があればリスニングも、さっと耳慣らしをしておきましょう!
前日に聞くべき音源は、公式問題集1択になります。

公式問題集では本番と同じナレーターが担当するため、耳を慣らすには最適です。
シャドーイングをやっていた方であれば、
- 声がついていけなかった
- どうしても発話に詰まってしまう
箇所を重点的にシャドーイングするのがおすすめです。

10分でもやっておくと違うので、ぜひ前日にリスニング脳を慣らしておきましょう!
文法・長文読解 | 直読直解の感覚を確かめる
リーディングについても、時間があればぜひ前日に復習をしましょう!
前日にやるべきことは、直読直解して読み進めていく感覚やスピード感の再確認です。
- パート5、6:過去に間違えた問題
- パート7:ダブル、トリプルパッセージの難しめの文章
こうした問題を適当にピックアップして、読めばOKです。
英文読解の感覚を確かめるのが目的なので、問題を解くのは時間があればでいいと思います。

直読直解は慣れるほどスピードが上がるので、前日に慣らしておきましょう!
関連記事 TOEICPart7【長文対策の勉強法】
少し早めに寝よう | 十分な睡眠時間を確保
仕事などで忙しく、前日に勉強する時間がなかったら睡眠を優先してください!
前日の睡眠は本当に大事で、本番のパフォーマンスに確実に影響が出ます。
「普段は6時間だけど本当はもう少し寝たい」という人は7時間寝るなど、ベストな睡眠時間を取ってください。
直前期で一番大切なのは、頭が完全にフレッシュな状態で当日の朝を迎えることです。

前日は睡眠優先で早めに寝ましょう!
TOEIC当日 | 私のルーティンと注意点

さあいよいよ試験当日!英語脳の適度な準備運動をして本番を迎えます。
参考書は全部家に置いて、ファイナルペーパーだけカバンに入れて、会場に向かいましょう!

以下で、私が毎回している試験当日のルーティンと注意点をシェアしたいと思います!
リスニング | 5分だけ真剣に!聞き流しはNG!
会場に向かう電車の中など、リスニングの勉強をするのはOKですが、聞き流しはやめましょう!
ここでの聞き流しとは、流れてくる英語の意味を考えずただBGMとして流している状態のことです。
私の経験上、聞き流しばかりしていると脳が「英語の音は適当に聞き飛ばせばいい」と勘違いします。

だから私は普段でも英語を聴くときはしっかり聴き、なるべくBGMにしないようにしています。
1時間聞き流すくらいなら、真剣に5分リスニングしましょう!上級者以外は多聴より精聴の方が効果的です。
リーディング | ファイナルペーパーで単語・熟語を総復習
リーディングは、事前に作っておいたファイナルペーパーだけでOKです!
前日にチェックしておいた暗記が不十分な箇所を中心に、丸暗記するつもりでやりましょう!

ここまで来たら、試験の間だけ記憶に残っていればOK!という潔さが大事です。
ファイナルペーパーは、問題用紙が配付されるギリギリまで読み込みましょう!
タイムマネジメント | 時間配分や解く順番の再確認
時間配分は試験直前に改めて、頭に叩き込んでおきましょう!
- パート5、6は1問何秒で解くのか
- パート5、6はそれぞれ何時までに終わらせるか
あたりは、確実に頭に入れておくべきです。

私はすぐ忘れてしまうので、こっそり手のひらにペンで書いたりしています、、
パート7から解くなど、順番通りに解かない人は、解く順番も始まる前に改めて頭に入れておくといいです。
【高得点者なら皆知ってる】10点上げるTOEICテクニック

直前期に押さえておきたい、すぐにできる即効性のある試験テクニックを紹介します。
門外不出で誰も知らない裏技とかではないですが、知らなかった人はこれを実践するだけで10点変わるはずです。

以下で書いている先読みは、これまでしていなかった人はペース配分が乱れるので、できる範囲でやってみてください!
パート1 | パート3,4の先読み
パート1では開始と同時に、急いでパート3、4の先読みをするのがおすすめです。
冒頭の問題説明(Direction)の部分を使います。
パート3、4ではイラストを使った情報量が多い設問があるため、先に準備をしておくのです↓

詳しくは以下の記事で書いているので、あわせて参考にしてください。
パート2 | 一瞬で不正解を見抜く裏技【悪用厳禁】
パート2では会話の受け答えが問われるパートですが、単語だけで答えている選択肢は正答肢になりにくいです。
以下の選択肢Aがそれです↓

実際に今私の手元にある公式問題集では、すべてこの法則が当てはまっています。
これは完全な裏技なので、盲目的な使用は厳禁です。

うまく聞き取れず、答えに迷ったときの判断材料の1つにする程度にしてくださいね!
パート4 | 絶対に先読みしたい設問がある
パート4では、全体的な主旨が聞き取れても、細部を聞き逃すと絶対に正解できない設問があります。
以下のような設問です↓

このタイプの具体的なセリフが書いてある設問は、必ず先読みして、セリフを頭に入れてリスニングに入りましょう!

全体が聞き取れるようになった人ほど、細部は盲点になるので注意してください!
マークシート用鉛筆を使う | 1分40秒の差が出る!
これをまだ使っていない人は今すぐ買いましょう!!
マークシート用鉛筆はお金で買える実力です。
私の場合、マークシート用鉛筆を使ったことにより、リーディングセクション100問をマークする時間を1分40秒短縮できました。

たった数百円で買えるので、持ってない人はぜひ!
選択肢で迷ったら | 本質的な解決策はこれ
選択肢に迷ったら、時間をかけずにサッと適当にマークするようにしましょう!
「答えに迷う=分からない」なので、いくら考えたところで正答率は何も変わりません。

むしろ迷っている時間が無駄です。
分からない設問はさっさとマークして運に任せて、別にもっと時間をかけましょう!
当日の流れ・スケジュール | 起床から終了まで

TOEICの当日の流れについて、私が毎回していることや注意点などをあわせて解説します。
一番大事なのは、会場には受付時間にあわせて到着し、会場の雰囲気に慣れておくことです。

以下で時系列に解説していきますね!
7~8:00 起床 | 出発時間から逆算して起きる
私の場合、出発時間から逆算して7~8時くらいに起きることが多いです。

子供が生まれてからはだいぶ早くなりましたが笑
早起きして勉強したい!という気持ちも分かりますが、肝心の本番中に眠くなる可能性があるので、おすすめしません。
当日の朝食と昼食の取り方 | 眠気をコントロール
朝はしっかり昼は軽め、が基本です。
試験が13時からで、
- ゆっくりお昼を食べる時間がない
- お昼をたくさん食べると眠くなる
ため、私の場合お昼はいつもカロリーメイトなど軽食で済ませています。

一部会場では会場内飲食禁止なので、どこで食事するかは事前に確認しておきましょう!
試験中にトイレに行きたくなるリスクを避けるため、コーヒーなどカフェインは10時以降は控えるのが無難です。
11:45 会場到着・受付 | 一番乗りで着き、雰囲気に慣れる
私の場合、11:45の受付開始と同時に入るようにしています。
会場は独特の緊張感があるので、できるだけ早めに入って空気感に慣れておくのがおすすめです。
直前の復習も、会場近くのカフェとかではなく、会場に入ってからするようにした方がいいです。

私も経験がありますが、時間が気になって集中できないんですよね。
会場に早く着けば、人も少なくて席も見つけやすいし、メリットしかないです。
ちなみに会場の様子はこんな感じ。

席に着いてからは、すぐ答案用マークシートで必要事項をマークしていきます。
マークする内容は以下のとおり。
- 名前
- 受験番号
- 簡単なアンケート
トイレも12:30の受付終了後は行けなくなるので、先に済ませておきましょう!

やることは全部先に済ませて、あとはゆっくりファイナルペーパーを眺めつつ時間が過ぎるのを待つのがおすすめです。
12:35 試験説明・音テスト | 聞こえにくい時は正直に言う
いよいよ始めるぞ!という感じで緊張感が高まってきます。
音が聞こえにくい場合は、正直に言いましょう!
声を上げて言うことにより
- 自分が聞こえにくい場合、他の人も同じことを思っている可能性が高く、感謝される
- よし!皆のために言ってやったぞ!と気分が高まる
というメリットがあります。

今まで1度もないですけどね笑
12:50~55 問題用紙の配付 | 筆記用具以外片づける
「これから問題用紙を配付します。受験票と筆記用具、腕時計以外のものはカバンにしまってください」
というアナウンスが入ります。

この瞬間までは、ファイナルペーパーを眺めていて大丈夫です。
問題用紙が手元に来たら、リラックスしつつその時を待ちます。
パート5、6の時間配分についても、このときに今一度確認しておきましょう!
13:00 試験開始 | 問題用紙のシールを上手に切るコツ
試験が始まったら最初にやることは、問題用紙のシールを切ることです。
私の場合、受験票をカッターのように使って、シールをサクッと切っています。

今までいろいろ試しましたが、これが一番キレイに切れます!
あとは冷静に粛々と、問題を解いていきましょう!
15:00 試験終了 | ネットで有名講師陣の感想を見る
TOEICは問題を持ち帰れないため、自分が何点取れたのか自己採点できません。
その代わり、毎回受験しているTOEIC界隈の有名人たちがネット上で講評をしています。
- 全体的な難易度はどうだったか
- パート別の難易度
を解説している人が多いです。

代表的な以下の3つを見ておけば、だいたいの傾向が分かると思います!
関連記事 TOEIC結果通知(アビメ)の活かし方
関連記事 TOEICのスコアが伸びない原因【2選】
【最終チェック】TOEIC当日の持ち物10個

大事な忘れ物をしないためにも、当日の持ち物は前日までにチェックリスト化しましょう!
以下は私のチェックリストですが、この他に必要なものがあればご自身で足してください。

最低限、受験票と免許証、筆記用具があれば何とかなります!笑
受験票、本人確認書類(免許証 etc.)

この2つは持って行かないと受験できないので忘れずに!
上の写真は私が以前受けて、手元に残っているものですが、この右側に証明写真の貼り付けと署名が必要になっています。

試験当日、会場で切り離すことになっているので、切り離さずに持って行きましょう!
写真は試験後に送られてくるスコア票に印刷されます↓

筆記用具 | マークシート用鉛筆も必ず!

私の場合、以下のものがすべてです。
- マークシート用鉛筆(メイン) 1本
- シャープペン(予備) 1本
- 鉛筆削り 1個
- 消しゴム 1個
マークシート用鉛筆は試験開始直前に、鉛筆削りで削っておけば、試験終了までもちます。

削りすぎて、芯が折れやすくならないように注意!笑
腕時計 | 私はアナログ派

会場に時計がある場合もありますが、必ず持っていきましょう!

受験票にも書いてありますが、置時計はNGです!
昔は試験用にピッタリ時間が分かるようにデジタル派だったんですが、今はアナログ派です。
羽織る服(シャツ、カーディガン等) | 寒さ冷え対策
真夏でも真冬でも、体温調節できる服は必ず1枚持っていくことをおすすめします。
- 夏:途中で羽織れるようにシャツ
- 冬:途中で脱いだりできるカーディガンかフリース
エアコンの効き具合は本当に会場によって違いますし、緊張で試験が始まったら暑くなってくることもあります。

問題が予想以上に難しくて、冷や汗が止まらないことも、、、
余計な雑念に振り回されないためにも、体温調節しやすい服装がおすすめです!
スリッパ | 会場によっては必要

スリッパが必要な会場の場合、受験票にその旨書いてあるので、チェックしておいてください!
直近に受けたTOEICの会場は専門学校で、スリッパ必携でした。(写真は私が会場に持っていった普段履いているもの)
会場ではスリッパを忘れた人も何人かいて、会場スタッフから使い捨てのシューズカバーを渡されていました。
こんな感じです↓


忘れたことの動揺とこの見た目の恥ずかしさで、10点ぐらい下がりそうです…笑
ハンカチ or タオル、ティッシュ

男性は普段持ち歩かない人もいると思いますが、
- トイレのとき
- 冷や汗をかいたとき
その他手が汚れたときなど、必需品です。
私は汗かきなので夏の場合は、ハンカチ以外にスポーツタオルも持っていきます。

タオルを首に巻いて試験を受けたこともありましたよ!
ノンカフェインの飲み物 | 麦茶が無難

TOEICのときはいつも、水筒に麦茶を入れて持っていきます。
私はコーヒー好きで、本当はコーヒーを入れたいのですが、トイレ対策でそこは我慢です。
その他緑茶やコーヒーなども、カフェインが入っているのでおすすめしません。
11時ぐらいに油断してとコーヒーを飲んだ時があって、試験中にトイレに行きたくなって集中力が削がれた失敗経験があります。

終わってから速攻でトイレに行きました笑
チョコレートなどおやつ | 試験開始直前に糖分補給!
私は問題用紙が配付される直前に、いつもチョコレートを食べています。
TOEICはすごく脳を使うタフな試験なので、2時間英語オンリーで試験が終わると本当に疲労感が半端ないです。
集中力を持続させるためにも、何かしら糖分補給をすることをおすすめします!

ダースかアルフォートが私の定番です!
ファイナルペーパー | 勉強道具はこれだけ

TOEIC試験会場での勉強はファイナルペーパーだけでOK。
ファイナルペーパーを作る前は、参考書を3、4冊会場に持ち込んでいましたが、今はこれだけです。
限られた試験直前の時間を最大限効率的に過ごすためには欠かせません!
平常心
最後の最後は、どれだけ冷静に最後まで心折れずに2時間を戦えるかが重要です。

TOEIC試験中は私でも、「やばい、、難しい、、どうしよう、、」みたいに思うことが何度もあります。
スタディサプリの英語講師 関正生先生も、こう言っています。
本当はぼく自身、毎回TOEICを受けるなんて、メチャクチャ嫌です。
GOTCHA! -TOEICで目標スコアを取る超効率的対策を徹底解説!【関 正生】
憂鬱(ゆううつ)でたまりません。
関先生でさえこんな精神状態なので、私たち凡人が緊張するのは普通なんです。
TOEICは始まる直前が一番緊張し、始まれば緊張感は一気に小さくなります。

どうせ実力通りにしかスコアは出ないので、開き直って頑張りましょう!
実力を100%発揮するカギは直前期の総復習にあり!

直前期をどう過ごすかで、スコアは30~50点ぐらいは最大で変わってきます。
英語は単語など暗記の要素も多いため、100勉強して理解したとしても、当日100覚えているかが重要になります。
そのための私の1つの提案がファイナルペーパーです。
一番もったいないのが、試験中に「あーこれ勉強したんだけど何だっけなぁ、、」というやつ。
私自身も何度かこれを経験したので、直前期の過ごし方を復習中心に変えました。
この記事がこれからTOEICを受ける方の参考になれば幸いです!

皆さんが勉強した成果をきちんと100%出せるように願っています!